押井守監督のアニメ映画『イノセンス』に登場した難解だった発言の数々の意味を考えました。
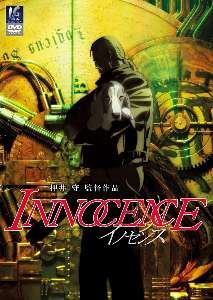
映画『イノセンス』は〈楽天TV〉で見られます!月額利用料無し、単品レンタル可能です。 ![]()
≪U-NEXT≫で『イノセンス』が見られます! 31日間無料キャンペーン実施中。
※このページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はサイトにてご確認ください。





引用以外の名言や小難しい台詞まとめ①
名言だと感じた言葉や、聞いていたら頭がこんがらがりそうだったセリフを文字にしました。
はじめに押井監督のイノセンスに関するインタビューでの発言を一部引用します。
それは全部わからなくたっていいんです。
その中で引っかかる言葉が一つか二つあれば。
全部分からせるのは、映画の構造上不可能だから。
時間はどんどん流れていくので、理解するスピードと映画のスピードを合わせようとすると、ある種の実りのない映画に必ず陥っちゃう。
今回は、バトーだったり荒巻だったり検視官のおばさんだったりに、いろいろなことをしゃべらせて、それぞれの相反する意見を出している。
これは、それなりに効果があって、引っかかってくれるんじゃないかと思ってる。 (引用:『アニメージュ』2004年3月号より)
観た後であれこれ考えて欲しい押井監督にとっては、理解するスピードと映画のスピードに時間差をつけるために、あえて難しい表現を多用したということなのでしょう。
引っかかりまくった私は見事策略にはまった模様です(笑)
大切なのは、これら引用や難解発言の意味を知ってどう感じたかだと思います。
荒巻:理解なんてものは おおむね願望に基づくものだ
荒巻:理解なんてものは おおむね願望に基づくものだ
バトーが「(事件の概要を)理解した」と言ったことに対して荒巻部長が返した言葉です。(会話の流れ的に屁理屈や説教っぽくも聞こえましたが)
『人間は信じたい事しか信じない』というような言葉があるように(ソースは忘れました、すみません)、理解もまた個人の願望に基づくもので、理解出来るか出来ないかは、理解したいかしたくないかで決まるということだと思います。
理解したかどうかは問題じゃない、とにかく働けという意味でもあるかもしれません。
ハラウェイ:人間とロボットは違う

©2004 士郎正宗/講談社・IG, ITNDDTD
人間とロボットは違う
でもその種の信仰は「白が黒でない」という意味において 「人間が機械ではない」というレベルの認識に過ぎない
工業ロボットはともかく 少なくとも愛玩用のアンドロイドやガイノイドは功利主義や実用主義とは無縁の存在だわ
なぜ彼らは人の形 それも人体の理想形を模して造られる必要があったのか
人間はなぜこうまでして自分の似姿を作りたがるのかしらね
(中略)
『子ども』は常に『人間』という規範から外れてきた
つまり確立した自我を持ち 自らの意思に従って行動するものを『人間』と呼ぶならばね
では『人間』の前段階としてカオスの中に生きる『子ども』とは何者なのか
明らかに中身は人間とは異なるが 人間の形はしている
女の子が子育てごっこに使う人形は 実際の赤ん坊の代理や練習台ではない
女の子は決して育児の練習をしているのではなく むしろ人形遊びと実際の育児は似たようなものなのかもしれない
トグサ:一体何の話をしてるんです?
ハラウェイ:つまり子育ては 人造人間を作るという古来の夢を一番手っ取り早く実現する方法だった そういうことにならないかと言っているのよ
トグサ:子どもは人形じゃない!
ハラウェイ検視官は、人形の自壊を「自殺」と表現したり「人形は使い捨てされるのがイヤで怒っている」と意見したり「子どもは人間ではなく人形に近い」というような意味の発言をしていることから、
人形(アンドロイドやガイノイド)と人間の区別があいまいで、どちらかと言えば人形の肩を持つタイプの研究者です。
また、ハラウェイ検視官がいるラボはマシンなどの品質保持のためか、温度が非常に低く保たれています。
トグサは寒がってコートのチャックを首元まで上げていますが、バトーとハラウェイ検視官は寒がる様子を一切見せません。
これは、ハラウェイ検視官もバトーと同様に体が義体だからです。
ハラウェイ検視官は、バトーの『人間と人形の捉え方』を顕著に表しているキャラクターと言えるでしょう。
トグサの「子どもは人形じゃない」という意見に対して、バトーは「デカルトは、幼くして死んだ娘の名前を人形に付けて生涯溺愛したらしい」と、ハラウェイ検視官を支持する発言をしています。
ちなみに『アニメージュ』のインタビュー記事で押井監督が、ハラウェイ検視官は取材でイタリアに行った時に出会った大学の先生がモデルで、彼女があまりにかっこいいおばさんだったので写真を撮らせてもらい、見た目もほとんどそのまま検視官として登場させたと話していました。
話題が飛びますが、ハラウェイ検視官はラボで煙草を吸いながら話していますが、温度管理も徹底しなければいけないこの部屋でタバコ吸っちゃって大丈夫なんでしょうか?
ヤニ汚れとか厄介そうだけど…と単純に疑問に思ってしまいましたw
喫煙行為はハラウェイ検視官が人間であることを示すものだったのだろうとは思いますが…
モデルにしたイタリアの先生がもしかしたら喫煙者だったのかもしれませんね。
バトー:生命の本質が遺伝子を介して伝番する
バトー:生命の本質が遺伝子を介して伝播する情報だとすると 社会や文化もまた膨大な記憶システムに他ならないし 都市は巨大な外部記憶装置ってわけだ
バトーがエトロフ経済特区の街並みを見た時の言葉です。
外部記憶って何となく難しい言葉ですが、簡単に言うと授業の内容をノートにとったり、何かを忘れないようにメモしたり、つまり頭で記憶するだけでなく何かに記録を残しておくことです。
ノートやメモがこの場合の外部記憶装置です。
人間が作った社会や文化、建造物などのあらゆるものが、当時の人々の技術や時代や価値観が反映されている『外部記憶装置』で、その社会や文化、建造物の中に人間の遺伝子が作り上げた仕組みや情報が残されてる、ということですかね。
キム:人間はその姿や動きの優美さに
人間の認識能力の不完全さは その現実の不完全さをもたらし そしてその死の完全さは 意識を持たないか 無限の意識を備えるか
つまり 人形あるいは神においてしか実現しない
いや 人形や神に匹敵する存在がもうひとつある
バトー:動物か
キム:シェリーのヒバリは我々のように自己意識の強い生物が決して感じることのできない深い無意識の喜びに満ちている
認識の木の実をむさぼった者の末裔にとっては 神になるより困難な話だ
キムとバトーの会話の一部です。
キムは人形を神と並べて崇拝し、動物も神や人形と同等の存在だと示し、一方で人間は人形、動物にも劣る罪深い存在だと語っています。
「人間の認識能力の不完全さは (中略) 人形あるいは神においてしか実現しない」の部分について
『人間の認識能力の不完全さは現実の不完全さをもたらす』は、人間が認識している『現実』は個々の主観(フィルター)を通しているものであり、
人間は自己意識が強いゆえに、物事を正しくあるがままに捉えることができない、『自己意識』という歪んだレンズを通して見ている『不完全な現実』ということです。
これは荒巻の「理解なんてものは、おおむね願望に基づくものだ」に起因します。
そして『不完全な現実』を生きている人間にとっては、その死も不完全になります。
なぜなら『完全な死』は『完全な生』によって可能となり、完全な生とはキムが言う『意識を持たないか、無限の意識を備えるか』のどちらかです。
つまり、『完全な死』を得られるのは、意識(認識能力)を持たない人形か、無限の意識(完全な認識能力)を持つ神様だけ、ということになり、キムの持論では認識能力が不完全な人間は完全な死を得られないことになります。
※こちらの解釈はコメントくださった まにょ様の解説を参考にしておりますので、参照元コメントも是非ご一読ください!ありがとうございました(;▽;)
※該当のコメントはこっちの記事の下部にあります。

バトー:生身の人形は死を所与のものとしてこれを生きる
引用だらけなのでこれも引用かと思いましたが、これはバトーオリジナルの台詞のようです。
キムが『魂を持たない生身』の美しさを伝えるために、死を恐れる人間の醜さを説明します。
そして、バトーが「言いたいことはわかった」という意味で上のセリフを言いました。
生身の人形は意識を持たない=生物に置き換えれば『死』とも言える。
なので、アンドロイドはある意味 死んだ状態で生まれ、死ぬまで死同然の状態で生きている、という意味なのかなと思います。
②に続きます!
この記事がお役に立てていたらハートマークを押してもらえると嬉しいです(^ ^)
・関連記事





その他の押井守関連の記事はこちらから
・参考サイト様一覧
・ちょんまげ英語日誌:孔子の論語 先進第十一の十二 未だ生を知らず、焉んぞ死を知らん
・150年目の移民:映画「イノセンス」全引用・名言まとめ

感想などお気軽に(^^)